節分と言えば豆まき!

私も、子供の頃「鬼は外・福は内」と言いながら楽しく豆まきをした記憶はあるのですが、そもそもの「節分の由来」や「豆まきをする意味」を知らずに親になってしまいました。
せっかくなので正しい由来を知って子供に伝えたいと思い、今回詳しく調べてみました。
- 1.節分の由来…
- 2.豆まきの由来…
- 3.豆まきの正しい作法・やり方は?
- 4.節分の由来を子供向けに説明するには!?
とこのような流れでお伝えしていきます。
1.節分の由来…
節分とは季節を分ける・季節の変わり目を意味しています。古くは「立春・立夏・立秋・立冬」4つそれぞれの前日のことを節分と言っていましたが現代では立春の「前日」のみを節分と言います。
→なぜ立春の「前日」を節分と言うようになったの?
その理由は・・・
旧暦では「立春」が新年の始まり。
旧暦では立春を1年の始まりと考ていました。
つまり立春の前日は今で言う大晦日、一年の最後の日と考えられていました。
- 節分(2月3日)…は大晦日
- 立春(2月4日)…は元日
(節分は年によって、2月2日だったり、2月3日だったりするので、上記の日にちはあくまで例です。)
新しい年がやってくる前に邪気を払い災いのない一年になりますように♪と願いを込めて豆まきが行われてきたそうです。
つまり4つあった節分の中でも一年で1番大きな節目である立春の前日(2月3日)が「節分」として今も残ったと考えられています。
2.豆まきの由来…
節分に豆まきをするようになったのは、室町時代ごろと言われています。でなぜ「豆」なのか?…。
主にこの4つが豆をまく由来とされています。
- 1.奈良時代に行われていた追儺(ついな)と言う行事で豆をまいて厄払いをしていてその風習が残った為。
- 2.昔から米や豆には邪気をはらう力があると言われていた。その中でも特に豆は大きいのでより悪をはらうのに最適とされた為。
- 3.昔話で「京都の鞍馬山(くらまやま)に鬼が出た時大豆を鬼の目に投げつけ鬼の退治に成功した」という話が残っている為。
- 4.豆には縁起の良い語呂合わせがある!
【魔(鬼)の目→魔目(まめ)】【魔を滅する→魔滅(まめ)】
古く昔、疫病や災害などの恐ろしい事は目には見えない「鬼の仕業」だと考えられていました。豆は鬼退治に大活躍し、また語呂合わせや縁起の面でも良いと言う事で、豆をまくのが現代でも残っています。
3.豆まきの正しい作法・やり方は?
豆まきの正しいやり方を知っておきましょう。

その前にちょっと豆知識を…(マメマメ言ってすみません(*_*;)
豆まきで使用する豆は必ず炒った豆を使いましょう!
豆を炒ることは魔目を射るという語呂合わせや、豆まきをした後拾い忘れた豆から芽が出ると縁起が良くないとされていて豆を炒っておくことでそれを防ぐことが出来るんです。

市販されている節分用の豆は、最初から炒って福豆(炒った豆)として売られていると思いますのでその場合は安心です(*^_^*)
前置きが長くなりました。それでは豆まきのやり方手順をお伝えします。
1.事前にする事
福豆を升に入れ豆まきをする直前まで、神棚にお供えしておきます。

神棚がない場合はタンスの上など高いところに白い紙を敷きその上にお供えします。
あと鬼は夜に出てくると言われているので、出来れば節分の日の夕方から夜に豆まきを行いましょう。夜の方が雰囲気も出ますよね!
2.豆まきスタート!!
いよいよ豆まきスタートな訳ですが…本来は家の主かその年の年男が「鬼は外」「福は内」と言いながら豆をまきます。
- 1.玄関から外に向かって「鬼は外」と言いながら豆をまきます。
- 2.各部屋の窓側から外へ向かって「鬼は外」と言いながら豆をまきます。
- 3.今度は玄関の外側から家の中に向かって「福は内」と言いながら豆をまきます。
- 4.各部屋の廊下側から部屋の中に向かって「福は内」と言いながら豆をまきます。
本来は女性や子供は「鬼は外」「福は内」の声掛けだけなんだそう汗。
豆まきで鬼をはらい、福を呼び込んだら豆まき終了です。
3.豆を食べることで鬼退治が完了!!
最後に自分の数え年(自分の年齢+1個)の数の豆を食べます。豆を食べることで鬼退治が完了になります。
以上「豆まきの正しいやり方」をお伝えしましたが、女性や子供は豆まき出来ないの?(+_+)ってちょっと寂しい気持ちになります…。今は時代も変わってきていますから、実際は自由に誰がまいても良いと思います!
次は小さな子供に、節分の説明をする時にどう伝えればいいかをお伝えします。
4.節分の由来を子供向けに説明するには!?

子供の年齢によって説明も違ってくるかと思います。特に子供が小さいうちは伝えても難しく感じる為簡単に説明してあげましょう!4~5歳なら下記の説明でよいと思います。
こんな感じの説明でいいと思います。
子供にとって大切なのは説明よりも体験だと思います。
今回は節分と豆まきの由来!子供向けに分かりやすく伝えるには!?という事をお伝えしました。
私自身も今日まで節分や豆まきの本当の由来を知りませんでした(汗)。子供にとって大切なのは、節分に豆まきをやったなぁという思い出だと思います。

皆さんも節分を楽しんで、今年も福をよびこんで下さいね~(^^)/
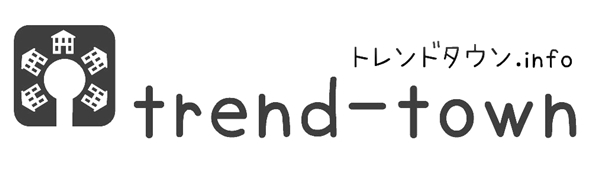
LEAVE A REPLY